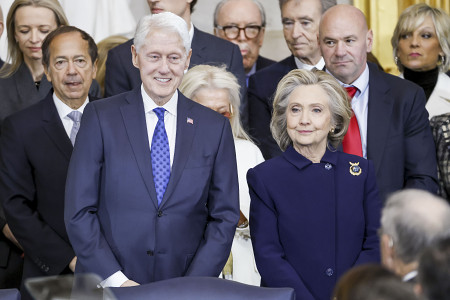県指定無形民俗文化財「豊田駒場の銭太鼓」 地元児童が披露

豊田市立駒場小学校(豊田市駒場町新生)の児童が9月30日、県指定無形民俗文化財「豊田駒場の銭太鼓」を披露した。
地元では「こまんばぜんだいこ」と呼ばれる「豊田駒場の銭太鼓」は、平安時代中期に都を追われた高い地位の貴族がこの地域に住むことになり、その貴族の娘が京都にいた頃に習い覚えた銭太鼓踊りを教えたのが始まりとされるもの。踊りに使う手持ち太鼓には文久銭12枚が入っており、タンバリンのように振ると音が出る仕組みとなっていることが名前の由来とされている。1957(昭和32)年に愛知県の無形文化財に指定され、毎年10月の第1日曜日に行われる地元・駒場神明社の秋祭りに五穀豊穣を願って踊るなど、さまざまなイベントに参加して駒場町をアピールしている。
同校では、この地域の伝統行事に親しみ、継承しようとする心を育むことを目的に、4年生児童が行ってきた総合的な学習の時間と音楽科の学習成果を発表する機会として、「豊田駒場の銭太鼓」の歴史を学び、夏休み前から練習してきた踊りを、この日の授業参観日に合わせて披露した。
始めに児童たちが、これまでに学んだ駒場銭太鼓に関する歴史についての発表を行った後、2グループに分かれ、保存会のメンバーの大太鼓の演奏に合わせて踊りを披露。銭太鼓を振って奏でる音に合わせて元気に踊る児童の様子を、保護者らがスマートフォンで撮影するなど、熱心に見つめていた。
児童が踊りを披露した後、保存会の代表者が「駒場には銭太鼓があるということを皆さんに知ってほしいと思い駒場小に来た。大きくなってこの駒場を離れる時が来ても、銭太鼓のことを思い出して、ずっと覚えていてほしい。10月5日の駒場神明社の祭りにも参加して、一緒に踊ろう」と呼びかけた。
児童が衣装の準備に対してのお礼の言葉や、「伝統を守っていくことの大切さを学ぶことができた」などの感想を話した後、最後は保護者らも加わり、参加者全員で銭太鼓を踊った。