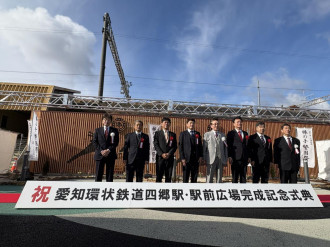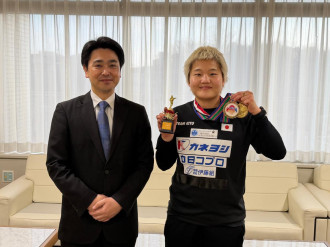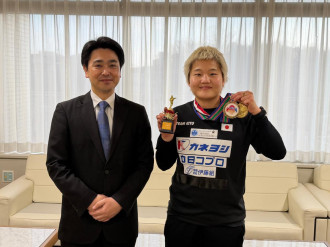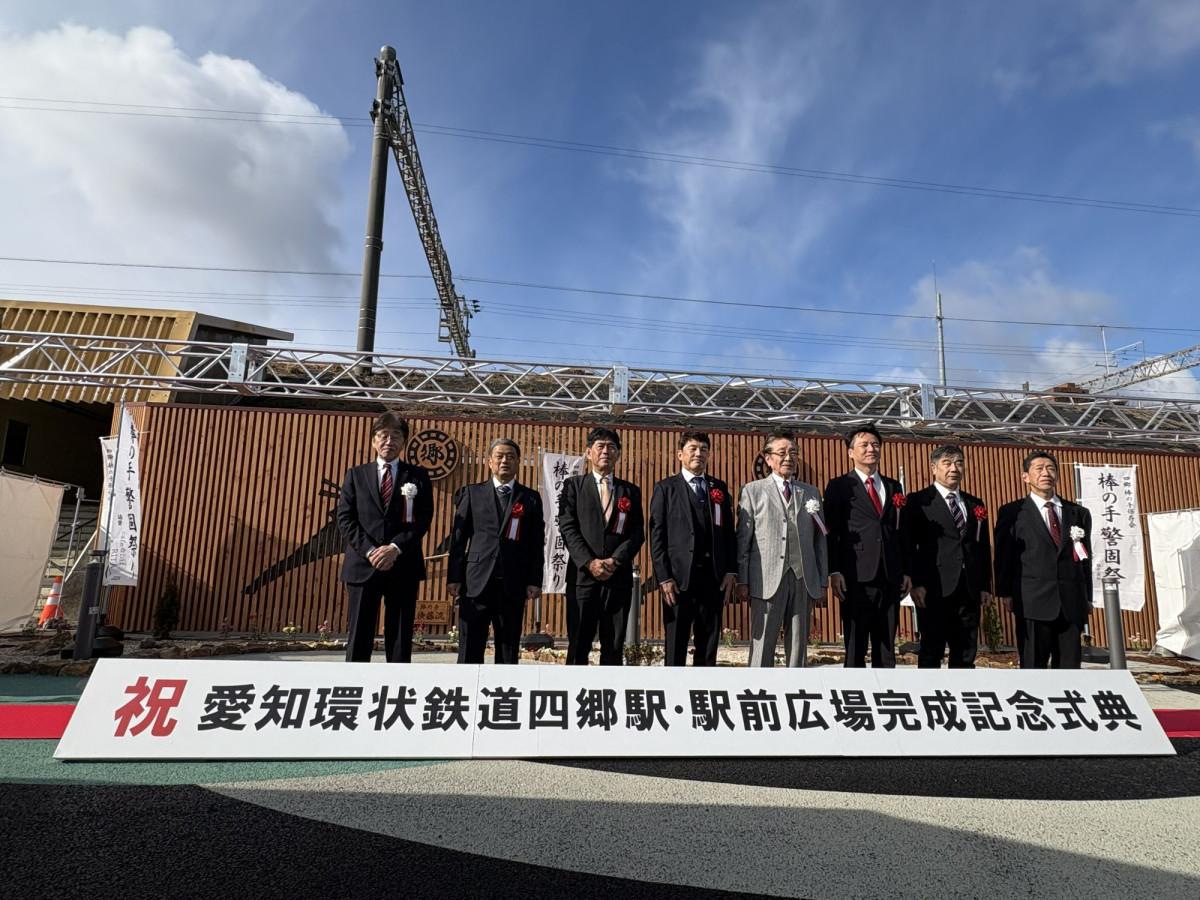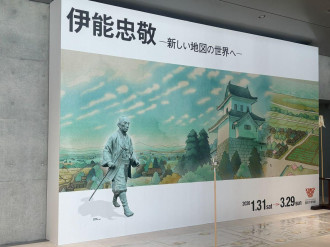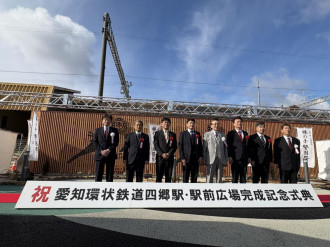足助八幡宮で本殿修理の特別公開 職人作業の体験会も

足助八幡宮(豊田市足助町)で4月19日、本殿保存修理工事の特別公開が行われた。
足助八幡宮本殿は673年に創建されたと伝えられ、檜皮(ひわだ)ぶき三間社流造の本殿は1907(明治40)年5月27日に国の重要文化財に指定されたもので、建物の健全性を回復するため、現在、修理工事が行われている。
今回の特別公開見学会は、保存修復を手がける豊田市が、地域住民や来訪者の文化財に対する関心と理解を深めてもらおうと開いた。
当日の見学内容は、ヒノキの樹皮を竹くぎで固定する「檜皮ぶき」という本殿の屋根の修復作業で、75センチほどの長方形に切り取られたヒノキの樹皮を12ミリずつ上にずらしながら重ねていき、60枚ほど重なった部分を、竹で作られたくぎを打ち込み固定するもの。
訪れた人は、通常見ることができない工事現場の様子を間近で見学し、職人が竹くぎを30本ほど口に含み、くぎの向きをそろえながら一本ずつ打ち込んでいく様子など、その素早く正確な職人の技に見入っていた。
見学会では、公益財団法人「文化財建造物保存技術協会」の職員が保存修理工事について解説し、ふき替えに使われるヒノキの材料や、職人の作業内容、工事前の屋根の状態などを説明。「竹くぎをなぜ口に含むのか」「檜皮をずらして重ねる際に、長さを測っているのか」など、職人の作業工程について熱心に質問をする人の姿も見られた。
このほか、屋根のふき替え体験も行い、「屋根かな」と呼ばれる専用の金づちの持ち方や、竹くぎの打ち方などを職人から直接教わり、参加した子どもが母親と一緒に竹くぎを打つ様子なども見られ、参加者は見学会を通して、文化財を保存する大切さを学んだ。